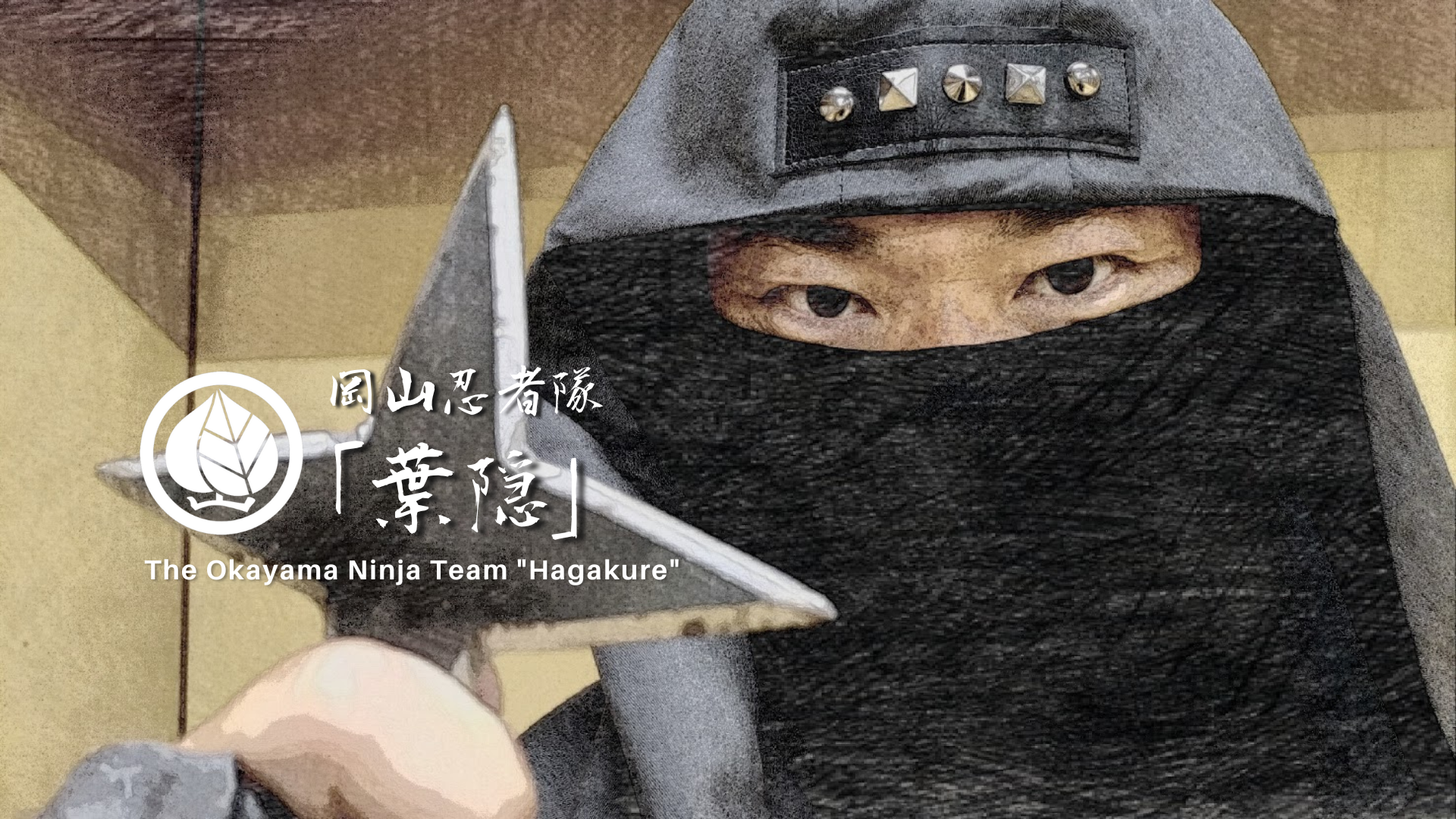忍者の象徴「手裏剣」──その進化と岡山忍者隊「葉隠」の手裏剣
忍者といえば、手裏剣。そう思う者は多いじゃろう。
戦国時代、忍者たちはさまざまな武器を使いこなしておったが、中でも 手裏剣 は「忍びの武器」としてよく知られておる。
しかし、現代の手裏剣のイメージである「十字手裏剣」や「六方手裏剣」のような形は、実は後の時代に生まれたものじゃ。
戦国時代に使われていた手裏剣は、棒手裏剣 と呼ばれるまっすぐな形状のものが主流であったのじゃ。
では、どうして手裏剣は今のような形になったのか?
そして、岡山忍者隊「葉隠」で販売しておる ゴム製の手裏剣 にはどんな種類があるのか?
今回は、この手裏剣の歴史と進化について語っていこうぞ。
手裏剣の始まり──棒手裏剣
戦国時代、忍者や武士が使っていたのは 棒手裏剣 という細長い金属製の手裏剣じゃ。
これは 短い鉄の棒を投げる武器 で、まるでナイフや針のような形をしておった。
なぜこの形だったのか?
それは、武士たちが日常的に持ち歩く武器として扱いやすかったからじゃ。
- 懐に隠しやすい:細長い形なので、衣服の中に忍ばせることができる
- 応用が効く:投げるだけでなく、突き刺したり、打撃武器としても使える
- 製造が容易:まっすぐな鉄の棒なので作りやすい
忍者はこの棒手裏剣を 敵を牽制する道具 として使った。
決してアニメのように、これだけで敵を倒す武器ではなかったのじゃ。
「十字手裏剣」「卍手裏剣」「六方手裏剣」はいつ生まれたのか?
棒手裏剣に比べ、現代の手裏剣は 複数の刃を持つ「板手裏剣」 という形状になっておる。
この形の手裏剣が登場したのは、江戸時代以降といわれておる。
この形が生まれた理由は 実用性よりも、視覚的な効果や遊びの要素 が強かったからじゃ。
- 投げやすい:どの角度で投げても刃が当たりやすい
- 見た目のインパクト:敵を威嚇するのに効果的
- 忍術のイメージ強化:娯楽や演武にも適していた
江戸時代には、手裏剣術が一つの武道として発展し、棒手裏剣だけでなく 多様な形の手裏剣 が作られるようになった。
岡山忍者隊「葉隠」のゴム手裏剣
岡山忍者隊「葉隠」では、実際に手裏剣投げ体験ができる ゴム製の手裏剣 を販売しておる。
これは 安全に手裏剣の技を学べる だけでなく、手裏剣の形状や歴史を知る機会にもなるのじゃ。
葉隠で取り扱っておるのは、以下の4種類じゃ。
① 十字手裏剣
もっとも一般的な形で、投げやすくバランスの良い手裏剣。
どこから投げても刃が当たるため、初心者にも扱いやすい。
② 卍手裏剣
卍(まんじ)の形をした手裏剣。回転する姿が美しく、見た目のインパクトが強い。
演武などでもよく使われる形状じゃ。
③ 三方手裏剣
三つの刃を持つ珍しい形。飛行機のプロペラのような形をしており、飛び方が独特なのが特徴じゃ。
手裏剣術を深く学びたい者におすすめじゃな。
④ 六方手裏剣
六つの刃を持ち、攻撃範囲が広い形状。投げるときの回転がスムーズで、安定しやすい。
迫力ある手裏剣投げを楽しみたい者に適しておる。
手裏剣の歴史を知ると、投げるのがもっと楽しくなる!
忍者の武器として発展した手裏剣。
戦国時代の棒手裏剣から、江戸時代の板手裏剣へと進化し、現代では 安全に遊べるゴム手裏剣 へと形を変えた。
形が変わっても、忍者の技術と知恵は変わらぬものじゃ。
手裏剣の歴史を知り、その技を学ぶことで、
より深く「忍びの世界」を体験できるはずじゃ!
岡山忍者隊「葉隠」の手裏剣道場で、ぜひ実際に手裏剣を投げてみるがよい!
それが、忍びの技を知る第一歩じゃ!